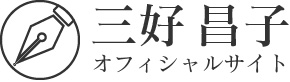幽玄の絵師 百鬼遊行絵巻
著書紹介
幽玄の絵師 百鬼遊行絵巻

あらすじ
都の闇に跋扈する、人ならぬもの鬼の如きもの・・・。
妖異が見える異能の絵師土佐光信は、将軍足利義政から、人心を惑わす妖物の正体を解くよう命じられる。御所をさまよう血濡れの女や、禍々しい「呪詛屏風」、影を喰らうものや、人の鳴き声を餌にするもの。将軍の心に取り憑き、裏から世を操る「鬼」・・・。
光信が怪異の謎を突き止めたとき、真に怖ろしいのは妖物か人か・・・。室町ミステリ。
解説
本書は、連作風長編である。「小説新潮」二0一八年二月号から一九年四月号まで断続的に掲載され、単行本になるときに「終の段」が書き下ろしで加えられた。物語の舞台は、応仁の乱前夜の混迷の時代。主人公は室町八代将軍足利義政に仕え、土佐流を確立する天才絵師の光信だ。心に壁を持たない彼は、人ならざる存在を見たり話したり出来ることから、さまざまな騒動に巻き込まれることになる。
冒頭の「風の段」は、足利義政から判じ物のような言葉を与えられ、絵を描くように命じられた光信が困惑する場面から始まる。困った彼が頼ったのは、新造された室町御所の南側の一番端にある月見高楼「梨花殿」の番人であった。異国から渡って来たらしい、唐朱瓶という老爺である。絵を描くためには義政の心を知る必要があるという唐朱瓶は、緋扇という女を紹介。そして緋扇の力で光信は、義政の少年時代の想い出を覗き見ることになるのだった。
足利義政は、毀誉褒貶の激しい人物である。兄で七代将軍の義勝が若くして死んだため、八代将軍になり、当初は政に意欲的に取り組んだ。疲弊した庶民の救済もしている。しかし有力な守護大名たちの争いは収まらず、大飢饉や災害も起こり、都までもが地獄絵図の様相を呈するようになる。そんな状況で、政へのやる気を失った義政は、作事。作庭に熱中。これにより銀閣に代表される、東山文化が生まれた。また、本書の主人公の光信や、狩野派の絵師の狩野正信や、能楽者の音阿弥なども抱えてた。為政者としては問題がありすぎるが、文化という側面から見ると、称揚すべき点も多いのである。
作者は、そんな義政像を、新たな角度から照らし出す。
さらに妖物のキャラクターにも注目すべき点がある。雨主や妖童子など、人間の願いを適えながら、どこかズレている。ズレているのに、世の中の真理を突いているようにも感じられる。真に怖ろしいのは妖物か、それとも人間か。妖物を絡ませることで、人間の在り方も、よりくっきりと浮かび上がってくるのだ。さまざまな読みどころを持った快作として、多くの読者にお薦めしたい一冊なのである。
令和四年二月 文芸評論家 細谷 正充