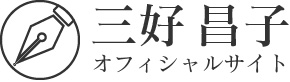幽玄の絵師―百鬼遊行絵巻―
著書紹介
幽玄の絵師―百鬼遊行絵巻―

あらすじ
混沌を極める百鬼夜行の時代を描く傑作。
著者コメント
「小説新潮」の掲載時は、「百鬼遊行絵巻」のタイトルで始まりました。単行本化が決まり、新たにタイトルを考えた時、まず頭に浮かんだのが、「幽玄」という言葉です。
「嵐の段」を書き終わった後、この小説の世界観が、「能楽」に通じているような気がしました。「能」もまた、生者と死者、または、妖物や精霊といった「化生(けしょう)の者」との関わりから紡ぎ出されていたことを思い出したのです。
学生の頃、「能楽」に関心を覚えた時期もありましたが、自ら関わることはありませんでした。それが、「百鬼遊行絵巻」を書いたことから、能について知りたいと考えるようになりました。
そんな折、通っていたカルチャーセンターで、「小鼓教室」が始まりました。まるで天啓のように小鼓を習い始め、そうして生まれたのが、最終話の書下ろし「終の段 笑い小鼓」です。
主人公は、絵師、土佐光信。彼の前には一風変わった世界が広がっています。「あの世」も「この世」も一つの「世」として、ただそこに在る。それを知る彼が、やがて、現在にまで残る「百鬼夜行絵巻」を描くことになる……?
解説
応仁の乱前夜を描いて心揺さぶられる
2017年、第15回「このミステリーがすごい!」大賞優秀賞『京の縁結び 縁見屋の娘』でデビュー以来、『京の絵草紙屋 空蟬の夢』『京の縁結び 縁見屋と運命の子』、本年七月に刊行されたばかりの『群青の闇 薄明の絵師』と、著者はこれまで四作の長編を発表してきた。(中略)
「風の段」「花の段」「雨の段」「鳥の段」「影の段」「嵐の段」「終の段」と、本書には七つの短編が収録されているが、それぞれに妖異が登場する仕掛けとなっている。
応仁の乱の前夜、怪異とくれば、司馬遼太郎の『妖怪』を想起する向きもあるだろう。が、両者の興趣はまったく異なる。剣で切り裂く司馬作品は、いわば娯楽性を重視した歌舞伎である。一方、絵筆を振るう本書の趣は幽玄の能―それも、神や亡霊、精霊など、超自然的存在の化身を描く「夢幻能」である。
本書は概ね、時系列に沿って展開するが、唯一「雨の段」は時代を遡り、光信の幼年期を描いている。嘉吉元年(1441年)、光信がまだ八歳の頃のエピソードだ。二歳で筆をとり、のちの世に土佐派土佐派三筆のひとりとと謳われる光信は、その才能の発芽をすでに垣間見せていた。彼がなにゆえ、人には見えぬ妖異の姿を視認するに至ったか。「絵にすることで、命を永遠に紙の上に留め」おくことができるという絵の本質を、幼心に刻むに至ったか。その過去を繙く物語である。ラスト、龍となり宙空へ消えていく鯉の化身に向かい、光信は声を張り上げる。「私は絵師になる。いつか龍になれるような、そんな強い絵師に…」
素晴らしいのは、言外に余情を漂わせる第一級の文章力。鏡花水月―その玄妙な筆致は、著者の著しい進境を感じさせる。なかでも、鳥を自在に操る鳥面冠者の正体を暴く「鳥の段」は出色。艶やかなイメージ喚起力といい、哀切極まる魂の叫びといい、綾なす情の機敏といい、まったくもって唸るほかない。そして、本書の胆となる終章。各段の伏線を回収しきったラストの一行の圧倒的な存在感は、まさに画龍点睛の一語に尽きる。魂が昇天したかのような読後感であった。
2019年 新潮社「波」10月号より 茶木則雄(書評家)
大森 望氏 絶賛!
室町ミステリーとしても
伝奇ファンタジーとしても超一流。
著者渾身の勝負作。
義政と光信のコンビが絶妙だ。