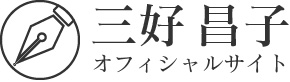むじな屋語蔵 世迷い蝶次
著書紹介
むじな屋語蔵 世迷い蝶次

解説
読み始めてまず目を引かれるのは、著者の御家芸でもある情景描写の見事さだ。…最初の二ページですっかり魅入られてしまった。映画のワンシーンを見ているかのようだ。景色だけでなく、空気、温度、雨が顔に降りかかるその感触まで、実際に体感したような錯覚を覚えた。……もちろん情景だけではない。その筆力は人物描写にも遺憾無く発揮されている。威厳のある住職と、可愛くも小生意気な小坊主。懐の深い庭師の親方。記憶を失ったまま働く朴訥な下男。中でも、衝撃の事実を知らされた人物の心が壊れていく描写は圧巻だ。…意外なところで明らかになる事実。思わぬところに仕込まれた伏線。知らされずにいた秘密。サプライズは随所にある。実に見事だ。つまり本書は、時代小説フアンやファンタジーフアン、SFフアン、ミステリーフアンまで、広範囲にお楽しみいただける小説なのである。
文芸評論家 大矢博子
著者コメント
人間長く生きていると、大抵の事は忘れてしまう。というより、頭の中にある引き出しの中に仕舞って、ほぼ思い出すことはなくなる。それでも、たまに、引き出しは勝手に開いて、思い出したくもないことを、再び、脳裏に蘇らせてしまう。
あの時、こうしておけば……。あの時、これしなければ……。幾つもの「もしも」がグルグルと頭の中を駆け巡り、今更、戻ることのない過去の時間に、大切な「今」を食いつぶされることになる。
時が戻せるなら、それも良い。その時は、大切な人たちに、言いたかった言葉を言えるだろう。それは、「ごめんなさい」だったり、「ありがとう」だったり……。
今でも思い出す度に、冷や汗が出る失敗もある。たとえ無事に済んでいても、最悪な事態になっていた時を想像してしまい、まるで実体験をしているように落ち着かなくなる。
心配性で考えすぎる傾向がある上に、想像力ばかり豊かだと、本当に、疲れてしまう。
むじな屋の壺に預けてしまい事は山ほどあるけれど、さすがに、深夜の髑髏探しはごめんだと思う。